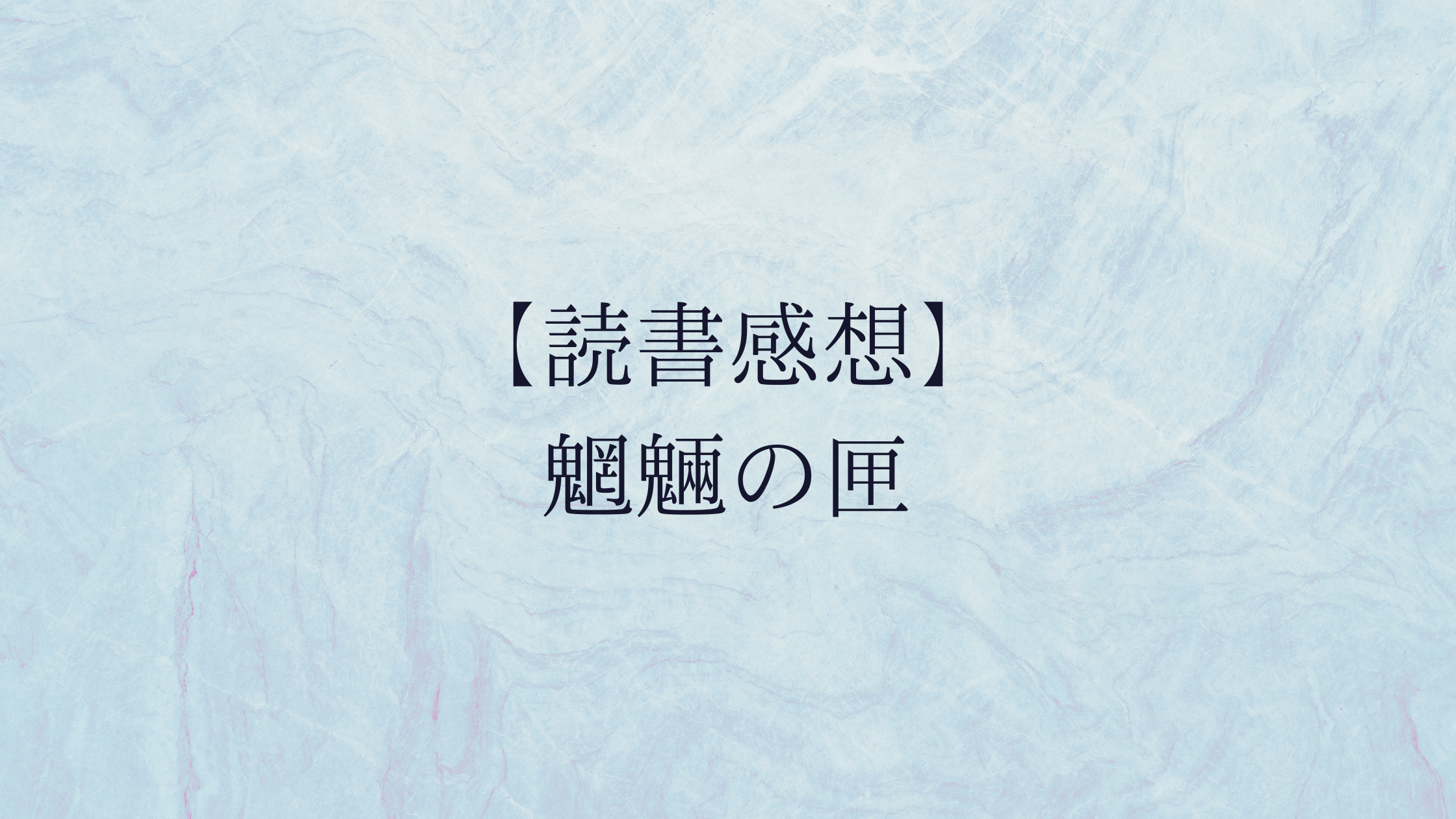タイトルや著者のことは知っていても、作品に触れたことがない、というものが多々ある。それは、小説、漫画、映画など、様々なジャンルにおいて、誰しもが抱えているものだろう。
私にとっては、京極夏彦作品がそれにあたる。どこの書店に行っても、京極夏彦作品は分厚くて、「読み切れるだろうか?」などと躊躇することが続き、なんとなく手を出せずにいた。京極夏彦作品を気になり続けて、もう何年かわからない。そんなことが続き、やっとの思いで、というとやや大袈裟だが、「姑獲鳥の夏」を読んだ。
今回、電子書籍版を購入したのだが、1冊がとても長いような気がするのに最後まで飽きることなく読めてしまう、というのは今回が初めてのことだった。恐るべし、京極夏彦作品の魅力よ。
「姑獲鳥の夏(1)」の後半くらいまでは、のんびりと読むつもりでいたけれど、「姑獲鳥の夏(2)」に突入するや否や読む手が止まらず、かなりのスピードで読み進めてしまった。
本作品において、関口巽、中禅寺秋彦、榎木津礼二郎のやりとりが、とてもおもしろかった。特に、中禅寺秋彦という人物は、家業は「武蔵晴明神社」の宮司であり、副業として憑き物落としの拝み屋をし、そのほかに「京極堂」という屋号で古書店を営んでいる、というところに興味が湧いた。
さて、ここまで本作品について、語っているようで語っていないのはなぜか。「おもしろい!」と思ったり、ストーリーの続きを知りたくて夢中になって読んだものの、どれを語ってもネタバレに繋がりそうだし、うまくまとめられそうにない、というのもある。こういった作品は、ネタバレなどに触れず、読み終えるのが最良だし、誰が見てもそうならないようなことしか述べたくない、というのも本音である。
ということで、「姑獲鳥の夏」を読んでみたら、視えるということが何を指すのか、呪われているということはどんなことなのか、そういった怖さを味わい、考えたような作品だった。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14dd7b53.32a3b09a.14dd7b54.ae7930e5/?me_id=1278256&item_id=11686748&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6923%2F2000000256923.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)